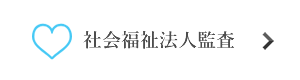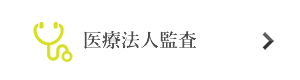会計監査をするなかで、「同じ内容の取引ですが、A拠点とB拠点で会計処理の方法が違うようですね」ということがあります。どのような取引でこのようなことが起こるのでしょうか。
社会福祉法人会計では、拠点区分別の貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書を作成する必要があり、多くの法人では拠点ごとに経理事務を行っていると思います。
毎月発生する収入、人件費、経費などの定型的な取引であれば、担当者が違っても、各拠点では同じように処理されていると思います。
一方、複雑な取引やたまにしか発生しない取引の場合、会計処理をする際に担当者の判断が必要となることがあります。判断の結果は担当者の知識や経験によって違う可能性があるため、会計監査の中で、このような判断を伴う取引について各拠点の処理を確認すると、冒頭のようなやり取りになることがあります。
判断が必要となるのは、固定資産の取得や改修工事に関する処理で多いのではないでしょうか。
具体的には、以下のようなものがあります。
【よくあるバラつき例】
1.工事契約の金額を複数の固定資産取得価額へ区分し、共通経費を按分する場合の計算方法
⇒台帳へ登録する固定資産の区分方法や取得価額の按分方法がA拠点とB拠点で違う
2.施設の改修工事に関する固定資産の取得と修繕費の判定
⇒同じような改修工事であるが、A拠点では固定資産に計上し、B拠点では修繕費に計上している
3.固定資産台帳へ登録する資産種類や耐用年数
⇒同種の固定資産を購入したが、A拠点とB拠点で違う耐用年数が台帳に登録されている
法人内で発生した同一の取引については同じ会計処理が実施されることが望ましく、処理にバラつきが生じている場合には、何らかの対応が必要です。
対応の一例として、上記のような担当者の判断が必要な取引で、かつ、決算に大きく影響する金額の大きいの取引については、法人本部でも拠点の処理を確認するということが考えられます。
金額の大きい取引については、法人本部でも決裁伺いなどで把握されていると思いますので、実際に会計処理をする前に拠点の担当者とコミュニケーションをとりながら処理を決定すれば、処理のバラつきを防ぐことも可能ではないでしょうか。
また、バラつき例で挙げたような判断の必要な取引については、法人の過去事例をストックしておき、判断に迷う際には過去事例を参照することで判断のバラつきを防ぐというような対応も有効と考えます。
さらには、定期的に発生する判断を伴う取引について処理の仕方をルール化しておけば、担当者ごとの判断の違いを防ぐことができるのではないでしょうか。
今年度に該当しそうな取引があれば、決算前に各拠点の処理を確認してみてはいかがでしょうか。